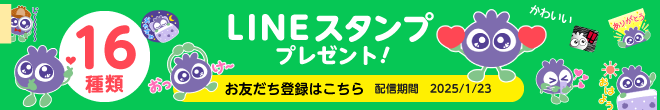カレープラントとは?
●基本情報
カレープラントは、地中海を原産地とするキク科ムギワラギク属の多年草植物[※1]です。乾いた丘や岩場、崖などに自生し、30~60センチぐらいの高さまで成長します。葉と茎にカレー粉のような香りがあることからカレープラントと呼ばれていますが、カレー粉の原料として用いられることはありません。また、苦味や香りも強いため食用では用いられることは少なく、スープの香りづけとして使用されます。
また、カレープラントの黄色い花や綿毛の生えたシルバーの葉は観賞用としても非常に価値が高く、ドライフラワーにも使用されます。カレープラントは、ドライフラワーにしても長時間色あせないため英語で「永遠の」という意味をもつエバーラスティングと呼ばれたり、「不朽の」という意味をもつイモーテルと呼ばれることがあります。
●歴史
カレープラントは美しい銀白色の葉をもっているため古くからイギリスで庭園に彩りを与え、寄せ植えなどに使われてきました。
●カレープラントの利用
・料理用
カレープラントが持つカレーのような香りは料理やピクルスの香り付けによく利用されます。生の葉はスープや煮込み料理などに少量加えるとカレーの香りが移り、よりおいしさが増します。調理する際に、煮込みすぎると苦味がでるので仕上げにサッと煮て取り出しましょう。また、葉を食べると胃に不調をきたすこともあるので必ず取り除くようにしましょう。
・芳香用
カレープラントはその特有の香りから他のハーブと混ぜてポプリとしても使用されます。また、カレープラントには、消臭効果があるためトイレや靴箱に置いておくのもおすすめです。
・観賞用
カレープラントは、葉や花の色が乾燥させても色あせないことからドライフラワーに最適です。また、黄色い花とシルバーの葉が印象的であることから花壇の縁取りなどにも効果的です。
[※1:多年草とは、茎の一部、地下茎、根などが枯れずに残り、複数年にわたって生存する草のことです。]
カレープラントの効果
●血流を改善する効果
カレープラントには、血流を改善するはたらきがあるといわれています。カレープラントの葉や茎から抽出した成分には血流をスムーズにする働きがあり、特に手や足先などの末梢血管[※2]の血流改善に効果が期待できます。血流がスムーズになることで、血流の滞りが原因で起こる頭痛や神経痛にも効果が期待できます。
●リラックス効果
カレープラントはリラックス効果をもつといわれています。カレープラントの精油には、感情を抑制し、閉鎖的になった心をオープンにしてくれる働きがあります。また、ストレスや緊張を緩和する働きもあります。
●傷の悪化や感染症を予防する効果
カレープラントは傷の治りを早めるといわれています。カレープラントの精油には、皮膚の再生を促す働きがあるといわれており、特に、あざや古い傷を治しきれいにする作用があります。また、抗炎症作用もあることから、ニキビや吹き出物の予防が期待できます。【1】【3】【4】
●腸内環境を整える効果
カレープラントは腸の不具合の改善などを目的にハーブティーとして伝統的に飲まれてきました。カレープラントに含まれる化合物が腸トラブルの改善に働きかけるとされています。【2】
[※2:末梢血管とは、手先や足先に向かって枝分かれしている血管のことです。]

カレープラントは食事やサプリメントで摂取できます
○血流を改善したい方
○心を落ち着かせたい方
○ストレスをやわらげたい方
○火傷や傷のダメージを抑えたい方
○あせもや湿疹を予防したい方
カレープラントの研究情報
【1】カレープラントから新たな数種類のフェノールを抽出し、これらの化合物において抗菌活性について評価を行ったところ、ヘテロダイマーに抗菌性が認められました。従って、カレープラントが地中海周辺で伝統医薬において傷の感染症予防に役立つと考えられています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23265253
【2】カレープラントのエタノール抽出物を細胞と動物を使い評価したところ、抽出物に含まれている2種類の化合物には鎮痙効果が認められたことから、カレープラントが腸のトラブルに役立つと考えられています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24140587
【3】カレープラントより新たに2種類のアセチルスチリルピロンを単離し、この2種類の化合物に緑膿菌が出す菌膜を張らせない効果があることが確認できました。この結果よりカレープラントには抗菌作用が期待できると考えられています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24094434
【4】カレープラントの地上部分の抽出物の抗炎症効果と抗酸化作用について確認を行ったところ、抗炎症作用が認められました。この抗炎症作用は炎症誘発酵素の阻害、抗酸化活性、副腎皮質ホルモン作用によると考えられています。
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11902802
参考文献
・はじめてのハーブ手帖 株式会社メディアバル
・ハーブスパイス館 田部井満男 小学館
・初めてのハーブ作り 小黒晃 世界文化社